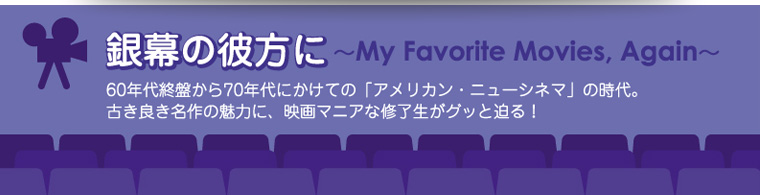第1回 『まごころを君に (原題:Charly)』(1968年)
Text by 村岡宏一(Koichi Muraoka)
映像翻訳本科「基礎コース・Ⅱ」に籍を置く受講生。北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"中。当年とって53歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
このコラムでは、私の心に残る「アメリカン・ニューシネマ」の時代の作品について自由に綴ってみました。名作には、いつ観てもかならず新しい発見があります。古き良き映画の魅力に気づけば、新作の楽しみ方も広がるはず。そんな気持ちでこのコラムを楽しんで下さい。
■ "ハッピーエンド無き時代"の希望と絶望
知的障害を持つチャーリーはパン工場で働いている。日々仲間から馬鹿にされ、知能テストを受ければ実験用のねずみ、アルジャーノンにも劣るほど低い結果であった。 そんなある日、チャーリーは彼の通う夜学の先生の推薦で、脳手術の被験者に選ばれる。 手術は成功した。チャーリーの知能レベルは手術を施した学者の予測以上に高まった。新たな"知能"を手に入れ、幸せを掴めたかのように見えるチャーリーだったが・・・。原作はダニエル・キースによる小説「アルジャーノンに花束を」。今日でも世界中に根強いファンを持つ異色の小説だ。この映画でチャーリーを演じたクリフ・ロバートソンは、第41回アカデミー賞で主演男優賞を獲得している。
チャーリーに脳手術を施した2人の学者が、その研究成果を学会で発表する場面がある。
チャーリーの知能は、当時としては「最高の科学者のレベル」にまで発達していた。そのため、発表後の会見の席に集まった科学者連中は、自らの知能では到達できていない疑問について、"天才"となったチャーリーに質問を浴びせかける。
将来、この世界はどうなるのか ? --。そんな難問に対しても、チャーリーは淀みなく答えていく...。
チャーリーの口から出た回答を、2007年の今、あらためて聞き直してみた。驚くべきことに、チャーリーの"予言"は、現在の社会の状況をほぼ正確に言い当てているのである。その具体的な内容に興味が湧いたという人は、ぜひ作品を観て確かめてほしい。
次に、役者の演技という視点でこの作品を見てみよう。クリフ・ロバートソン演ずる手術前のチャーリーは、言葉がスムーズに流れず、しゃべるたびに口元は歪み、動作は緩慢で目の焦点も定まっていない。映画とわかっていても同情の念を禁じえないほどのキャラクター作りは、まさに"主演男優賞クラスの演技"と言えよう。脳手術を受けた後に、知性を帯び、人格ごと変化していくチャーリーを完璧に演じきっているのにも脱帽だ。馬鹿にされていたチャーリーが、周囲の者たちに認められていくシーンは、何度見返しても痛快な気持ちになる。
この作品が優れているのは、人間の本質に関わる問題にも踏み込んでいる点にある。つまり、「知能と精神のバランスの問題」だ。
知識が身についても、精神面の成長がそれに追いつかない人間はどうなるのか--。この作品ではそれを、「チャーリーの目線」を示すカメラワークで赤裸々に表現している。卓越した知能を得ながら、ごくごく日常的な「性的な衝動」との葛藤で、心の均衡を失うチャーリー。その心象を、例えばカメラが女性を追うアングル ( チャーリーの目線 ) で、観る者に疑似体験させる。
当時の話題作、特に「ニューシネマ」と呼ばれた一連の作品群には、ハッピーエンドはまず期待できない。もちろんこの作品も例外ではない。「映画とは、その時代の空気を織り込み、反映するもの」という普遍の定義に従えば、この映画が生まれた時代は「美しいエンディングを容認できない時代」だったのだ。
1960年代後半、ベトナム戦争は泥沼化の様相を呈し、米国で起きた学生運動のうねりは、日本を含む世界中の国々に広がっていった。学生や市民の中からは、世界の幸福を願う熱いマグマのような善意があふれ出してはいたものの、その想いがどこに流れ着けばよいのかがわからない。何かを変えなければいけないという焦りはあるが、明日がよく見えない...。
「閉塞感と明日への希望が交差する不思議な時代」を象徴する映画の一つが、「まごころを君に」である。