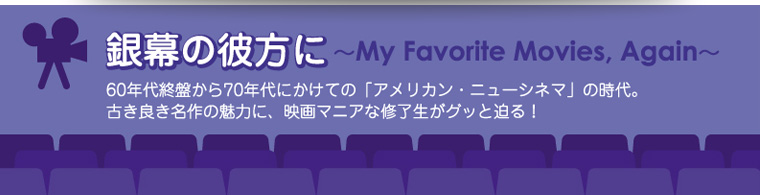第6回 『時計じかけのオレンジ』(1972年)
Text by 村岡宏一(Koichi Muraoka)
映像翻訳本科「実践コース」に籍を置く受講生。北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"中。当年とって54歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
【作品解説】 1999年に亡くなった鬼才スタンリー・キューブリック監督の作品です。「2001年宇宙の旅」(1968年)、「博士の異常な愛情/または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか」(1964年)を含む彼のSF3部作の1本です。
傑作の誉れも高く、1971年のアカデミー賞4部門にノミネートもされているのですが、一方で否定的意見も存在する異色作でもあり、紹介してよいものかどうか...と迷いました。
隣の席の外国人は一言「No!」と叫び、上映中の館内から出て行った。
厳しかった受験戦争が終わり、何とか私を受け入れてくれる大学が決まった。埼玉県草加市の獨協大学である。
入学年度は1972年。
入学直前の2月には、連合赤軍による「あさま山荘事件」が勃発する。その後連合赤軍内部のリンチ殺人事件が発覚し、リーダーの永田洋子をはじめ、幹部全員が逮捕された。
この事件を機に、60年代から70年代の前半に吹き荒れた安保反対運動はほぼ終焉することとなる。
祭りは終わった...、そんな年であった。
学内は時折、左翼系学生会と右翼系体育会の小競り合いがあったものの、平穏な時間が流れていた。しかし取り囲む空気は、学生運動の挫折感からくるのだろう、鬱屈した何かをまだ含んでいた。
だが、そんな学生たちのセンチメンタリズムには目もくれず、日本の景気は高度成長真っ只中であった。アメリカ資本の日本市場への本格参入が始まったのもこの頃からだ。前年の71年には銀座三越にマクドナルド1号店がオープンし、2年後の74年にはセブンイレブン1号店が江東区豊洲にオープンする。マックシェイクを初めて飲んだのも大学1年のときである。何とも飲みづらいドリンクだと思った。
そんな状況で方向性を見失っていた日本のキャンパスでは、4年のモラトリアムを享楽的に謳歌しようという気運が支配的であった。今にして思えば、大学がレジャーランド化するはしりの時期だったのかもしれない。
「時計じかけのオレンジ」を見たのは、そんな大学1年生の春の、ある日曜日である。奨学金を貸与されている貧乏学生ではあったが、当時、映画のメッカであった日比谷のロードショーに足を運んだ。鑑賞料は1000円前後であっただろうか。
高校時代に読んだ映画史に関する本に、「博士の異常な愛情/または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか」という異様に長いタイトルと、その監督であるキューブリックが紹介されていたことを覚えていた。「時計じかけのオレンジ」というわけのわからないタイトル、公開時のポスターもかなりエキセントリックであった。ひどく危険な匂いがした。
そんな直感で見ることを決めたのだが、この映画、とんでもない代物であった...。
■ 「あちら側」からは常に、どこからか見られている
映画を見終わると私たちは様々な感慨を持つものである。「面白かった」、「ドキドキした」、「スカッとした」、「泣けてきた」などなど。 ところが人間の感情というのは、そう単純なものではない。映画の製作サイドは、作品にとっておあつらえ向きの感情(悲劇の恋愛ものならば大いに泣いて下さい、とか)を狙い撃ちにする。しかし、稀にだが、観客の「できれば触れて欲しくない、思い出したくもない」という部分を心の底から引きずり出し、鼻先に突きつけることを楽しんでいるかのような監督もいるのだ。
私はこの作品がそうだとは、あえて断定しない。大学生であった私がこの作品に感じた嫌悪感や不快感、不安感、警戒感を、なかには歓迎し、楽しめる人もいるだろう。百歩譲って私の得た感覚がおおよそ正しいものだったとしても、映画として悪い作品だとは決して言い切れない。
映像を見て湧き出た感情はあくまでも「感情」である。後になってから見えてくるものに気づき、その作品が意味する真の価値に感動し、監督の力量をあらためて評価する、という経験は誰にでもあるだろう。
ただ、次のような出来事が、この映画の鑑賞中に実際に起きた。
主人公アレックス(マルコム・マクダウェル)が仲間の裏切りにより警察に逮捕され取調べを受けているシーン。警察の一人が彼の顔に唾を吐きつけた。その瞬間、私の隣に座っていた中年の外国人の女性が、「No!」と低くつぶやいたのだ。続けて顔を左右に振りながら席を立ち、そのまま退場してしまったのである。ひどく当惑し、悲しそうな顔をしていた。
観る者の理性や常識をあざ笑い、揺さぶりをかけ、挑発する映画。あの外国人女性のように、誰もが拒否反応を起こす、というわけではないだろう。例えば、普段は良識派を気取っている人間が、いつのまにか映画のなかで暴力を振るう人間や人権無視の暴挙を働く人間に共感していたとしたら...。そして、そんな自分に気づき、混乱し、途方に暮れているとしたら...。
そんなふうに流されやすい私たちが住む「こちら側」の世界。しかし、私たちからは決して見えない「あちら側」の住人は、頼んでいるわけでもないのに常に私たちを監視し、私たちが彼らを悩ませる方向へ行かないように、さりげなく軌道修正を行っている。
気をつけていないと、彼らの"指導"は、常道を外れることがある。いつの時代でも、どこの国でも。あの学生運動が、時の体制の手によって風の中の塵と消えたように...。
ラストシーンで、アレックスは"完璧"に「こちら側」へ戻ったことを報道陣の前でアピールする。記者たちと受け答えをしながら、カメラのフラッシュを浴びていたその時、彼の気持ちはゆっくりと高揚し始め、表情が少しずつ、しかし確実に変化していく...
このアレックスの表情はどう表現すればよいのだろう、
そして最後までこの作品を見てしまったあなたはいったい何を感じるのだろうか...
まさしくキューブリックを鬼才と呼ぶにふさわしい作品である。