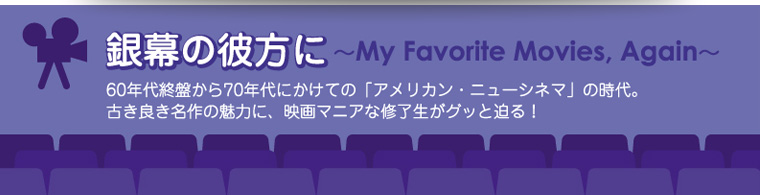第15回 『ラスト・ショー』(1971年)
Text by 村岡宏一(Koichi Muraoka)
映像翻訳本科「実践コース」を2008年3月に終了。在学時は北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"であった。当年とって55歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
【作品解説】「ラスト・ショー」(1971年)――ピーター・ボグダノヴィッチ監督による'51年前後のテキサス州の田舎町を舞台としたモノクロ映画です。それこそ高校生のフットボールの結果が翌日町中の話題に上るくらいの小さい町で繰り広げられるさまざまな恋愛模様、人間模様を描いています。
スクリーンの上で躍動する若者たちが躊躇することなく、好奇心もあらわに突き進むさまを見ていると、心の奥深くに仕舞いこんでいた(なるべく触れたくない)自分の青春の証をそれと重ね合わせてしまうのは私だけでしょうか。何も無いということが唯一の財産だったあのころを特別の感慨とともに思い起こさせてくれる名作です。
原題の「The Last Picture Show」 は、若者たちの社交場でもあった映画館が取り壊されることになり、「赤い河」(1948年、ハワード・ホークス監督、ジョン・ウェイン主演)が最後の上映作品(The Last Picture Show)として劇中映画に取り上げられているのですが、両方をご覧になるとボグダノヴィッチ監督が数ある映画作品の中からなぜこれを選んだのかが良くわかります。
第44回アカデミー賞でベン・ジョンソン(役名サム)が助演男優賞、クロリス・リーチマン(役名ルース)が助演女優賞を受賞しています。
第15回:求める心と応える心、そして通い合う心
1971年、ある歌謡曲が日本国中を席巻した。当時40代半ばに差し掛かっていた俳優で歌手の鶴田浩二が歌う「傷だらけの人生」 である。曲冒頭と曲間の鶴田のモノローグ、というよりほとんどつぶやきに近いセリフが人々の心を捉えた。戦争が終わって25年が経過し、高度成長期を迎えて繁栄に浮かれている日本を憂い、嘆くセリフだ。しかし、そう感じるのは(自分が古い人間だからなのか)、と自虐的に言い放つ姿がなぜか世代を超えて大きな支持を得た。
こんな感じだ。「古い奴だとお思いでしょうが、古い奴こそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中、右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」。
当時の日本はアメリカに追従する形で農業国家から工業国への急速な変化に国全体が振り回されていた。そのような変化を良しとしない世代の代表が鶴田浩二だった。戦時中特攻兵として大勢の仲間を見送り(実際は飛行機の整備兵だったらしい)、死に切れずに終戦を迎え、敵国の価値観を唯々諾々と受け入れ、日本人の自意識、美意識、倫理観が次々に切り捨てられてアメリカナイズ、つまりかぶれていく現状に対し、鶴田の世代は我々には想像もできない危機感を抱いたのだと思う。セリフもある荒廃しつつあった地方への憂いは、40年後の現在、それが現実となって我々の目の前にある。
食料自給率が40%を切り、農業の後継者が不足し、地球は温暖化の一途をたどっている......おまけにアメリカ発の金融恐慌によって、今日の日本の景況感は「過去最悪」に陥ったと、報道関係は連呼している。
この地球レベルの危機を、鶴田は草葉の陰からどう見ているのだろうか。
2番の歌詞の前には、男女のあり方に言及したこんなセリフもある。「好いた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。好いた惚れたは、もともと心が決めるもの...こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね」。
戦後、恋愛結婚が徐々に増え、見合い結婚が古いという考え方が広がってきていたさなかに、鶴田は自由恋愛至上主義の狂騒を「けだものごっこ」と吐き捨てたのである。
「ラスト・ショー」の男女関係を言い表すのに、鶴田のセリフ以上にあてはまる言葉はない。
高校生が夫ある女性と関係し、女子高生が自分に合う男を執拗に捜し、二人の男子学生はその行動に翻弄され友情が壊れそうになり、社長夫人が夫の会社の人間と関係し、娘も同じ人間と関係する。その社長夫人は昔・・・。自らを抑えることを知らないかのように、自己の欲求を満たそうとする登場人物たち。当然傷つく人間もいるが、傷が癒えればめげることなく再び立ち上がる。そのバイタリティーには頭が下がる。
正しいから勝つのではなく、勝ったから正しいという弱肉強食の国、米国においては、自分のパフォーマンスで相手を組み伏せることができなければ、それは負けを宣言するに等しい。敗者には何も与えられないことをこの国の人々は本能的に認めている。
私個人のことで恐縮だが、2月から実家に戻って父親と二人暮しをしている。父の体力が落ちて一人暮らしが無理になったためだ。そんな父も考えるほうは日常生活と意思疎通にはほとんど不便はない。現在の日付と時間の認識が多少あやふやになっているくらいだ。同じことを何度も繰り返して言うのでときどき閉口するが、過去の出来事は驚くほどはっきり覚えている。
筋力が落ちているのと手の動きが多少不自由なため家事全般をスムーズにできないので、私がすべてをこなしている。やればできるもので今ではほとんど苦にならない。慣れとはこんなものかと自分でも驚いている。
そんなある日、夕食後二人でテレビを見ているときだった。不意に父が、「母さん一人で留萌から来たんだわ」 とつぶやいた。平成7年12月に亡くなった母との馴れ初めを急に話し始めたのだ。よく聞いてみると、昭和26年(1951年)6月に、留萌(北海道留萌(るもい)市)に住んでいた父の妹の嫁ぎ先から、年頃の娘さんがいるから会ってみないかとの勧めがあり、父はそれに気軽に応じたという。当時父は34歳、母は28歳であった。
約束の日時に深川の停車場(ていしゃば:今のJR駅)に行くと、きょろきょろ不安そうに周りを見渡していた若い女性がいたので「正木(まさき:母の旧姓)さんかい?」 と父が尋ねると、母はほっとした表情で「そうです、村岡さんですね」 と言い、ぺこりと頭を下げた。
当時の父は抑留先のソビエト連邦共和国(現:ロシア共和国)から引き揚げてきて間がなかった。就職したてでもあり懐の中は寂しかったはずだ。しかし元来"いいふりこき(北海道方言:カッコウをつける人)"なため、一張羅を着込み、昼食用の金も用意して迎えに行った。
挨拶が終わり食事に誘おうとすると、母は「少し散歩しませんか、いい天気ですし」と言って石狩川の堤防に向かって歩き始めた。父は機先を制せられ少し驚いたがそれに逆らいもせず、二人並んで歩いていった。
石狩川の堤防は深川の駅から南に向かって歩くと5分ぐらい先になるだろうか、通り沿いの町並みはすっかり変わったが道筋は今も当時も同じはずだ。
堤防に着くと母は用意した新聞紙を草の上に広げ父に座るように勧めた。父と母が並んで座りしばらく川面に目をやっていたとき、母はハンドバッグの中から二つの包みを取り出すと父に一つ手渡し、「お昼にしましょう」と言った。包みの中には、母お手製のおにぎりが二つ入っていた。父はそのときつくづく感心したという。
食事の後3,4時間二人は取り留めない話をしてその日は別れた。
これが二人のお見合いだった。
世話人もなく豪華なホテルを使ったわけでもなく、風がそよぐ青空の下で手弁当を分け合い、言葉を交わし、はじめて出会ったその日に心を通い合わせたのだ。
数日後、父は紹介者に結婚承諾の返事をした。その後結納の儀なども格別行わず、翌年の春に父の実家で近親者と近所の親しい人たちを招待し、簡単に結婚式がとりおこなわれた。"お見合い"の日から挙式の日まで、二人は一度も顔をあわせることはなかったそうである。当然新婚旅行もなく、家庭用電化製品など国内では存在さえしていない頃で、文字通りないない尽くしの中、父が住んでいた市内の棟割長屋で新婚生活が始まることとなった。
私も産婆に取り上げられそこで生まれて小学校の低学年まで暮らしていたのでぼんやりと覚えているが、一つの部屋と炊事場、トイレは共同、おまけに日中も満足に日がささないうす暗い部屋だったような記憶がある。
今から見れば過酷としか言えない環境で二人が心に刻み込んだのは、お互いを伴侶として選んだこと、そのことこそが目の前にある事実であり、生きていくことは好いた惚れただけではどうにもならない、ということだ。そこからでも努力して必ず幸せをつかもうと、二人は自分たちに言い聞かせ、それを信じてひたすらに生きた。
私を含めた3人の子供が独立して手が離れた頃、気分的に余裕ができたのか、母は気心の知れた友人とグループを組んで国内旅行に出かけ始めた。お土産がよく私のところにも送られてきたので、それを見ながら(今回は九州か、今回は東北に行ったんだ)と、母の旅姿を想像したものだった。
それから数年後、脳梗塞が原因で母は倒れ、3年間の入院生活の後、平成7年12月、父に看取られこの世を去った。父は母が入院してから亡くなるまで運転免許を持っていなかったので、JRとバスを乗り継ぎ片道2時間かかる病院までの道のりを一日も欠かさず見舞いに通った。
父が病室に顔を出すと、毎日来ているのに母は「父さん、父さん」と声を掛け、いつも目に涙を浮かべて喜んでいたそうである。
平成14年に迎えるはずだった二人の金婚式まで後7年だった。