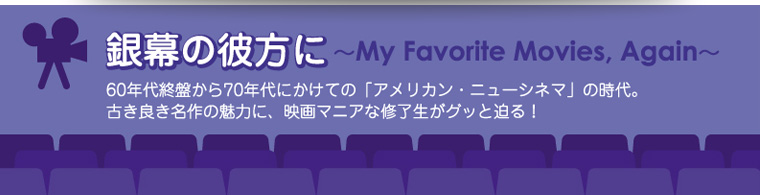Text by 村岡宏一(koichi Muraoka)
映像翻訳本科「実践コース」を2008年3月に終了。在学時は北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"であった。当年とって55歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
【作品解説】「オール・ザット・ジャズ」(1979年)――ブロードウェイ・ミュージカルの振付と演出を手がけていたボブ・フォッシー監督の自伝的な作品です。第52回アカデミー賞9部門にノミネートされ4部門で受賞したほか、カンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得しています。この年のパルムドールは2作品に与えられました。もう1本は黒澤明監督の「影武者」で、直前までこの1本に決まっていたのですが、審査委員長だったアメリカの俳優カーク・ダグラスが東洋の島国の作品に最高栄誉賞を授与することに納得できずごねまくり、結局ダブル受賞になったという噂が囁かれています。
映画は監督自身を投影させた売れっ子振付師ジョー・ギデオン(ロイ・シャイダー)の毎朝のイニシエーションから始まります。ビバルディーのクラシックナンバーを流しながらシャワーを浴び目薬をさし、覚せい剤を胃袋に流し込んだ後に身支度を整えて鏡の前に立ちます。そして寝るとき以外は決して口から離すことはないタバコをくわえて鏡に映った自分に向かい「It's a show time, folks.(ショータイムだ)」とつぶやくのです。スクリーンに彼の抱く幻影が投影された後、ジョージ・ベンソンの歌う「オン・ブロードウェイ」のメロディーをBGMに、シーンは新作ミュージカルのオーディション会場に移ります。たった5名を選ぶために何百人もの人間が次々にふるい落とされていきます。志望者たちとの対話の中で、彼の資質と性格、人間性が浮き彫りになっていきます。
自らの作品に輝く天賦の才、そして分け隔てなく(手当たりしだい?)女性たちと関係を結ぶ退廃的愛憎劇。ショービジネスの光と影の狭間を漂いながら、彼の体は確実に蝕まれていきます。彼の心に浮かぶ過去の回想と幻想シーンを絡ませながら、映画はやがてファンタスティックな終焉を迎えます...。
第16回:「生の証」を芸術表現に求めて
2000年だったと記憶している。私が所属していたあるアマチュアバンドのリサイタルでのことだ。オープニングからの数曲が終わったが、聴衆の反応は今ひとつだった。空気が温まってこないそんな中でゲストがソロプレイをする曲順がやってきた。
スポットライトの当たるセンターマイクへ彼は歩みより、おもむろに最初の1音をトランペットから発したときだった。その音が会場を包み込み客席が一瞬にして静まり返った。曲はアメリカ人が最も好むと言われている「Star Dust」のバース(前歌)の冒頭の音である。しかし、アメリカ人にはウケるかもしれないがここは日本、しかもアマチュアバンドのリサイタルである。親戚や知人、職場の仲間など、客席を見渡しても失礼ながらジャズに精通していると思える人がそれほど見受けられるわけでもない。この曲を知らない人がほとんどのはずだ。
にもかかわらず、私たちは彼が演奏を始めた瞬間、彼の作り出した音の世界に引きずり込まれたのである。そしてその演奏が終わった瞬間、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。
そのときまで、私は音楽の持つ力というのを感じたことがなかったわけではない。数多くのプロの生演奏に接し、何度も心が震えたことがある。しかしこの日の感動は異質だった。シングルノート(一個の音)である。旋律とか、連続するリズム、ハーモニーではなく、ただ一個の少し長めの音だ。
音そのものにこれだけ心を揺さぶられたのはそのときが初めてだった。
私も下手の横好きでトロンボーンという金管楽器を何年も経験していたわけだが、本質的に「楽器奏者とは何を目指すべきなのか」を見せつけられてしまった。それは音それ自体が美しくなければならないということ、今出している以上のものを常に心がけなくてはいけないという、頭でわかっていたつもりの真理だった。
「オール・ザット・ジャズ」('79年)の中で、主人公のギデオンが振り付けしたダンスを、ダンサーたちがスポンサーのお偉い人たちに披露するシーンがある。陳腐な、いかにもミュージカルナンバーというメロディーだが、彼は自ら選んだダンサーに過激な振付けを施し、演じさせる。そのダンスシーンは私たちを夢幻の世界にいざない、彼の異才を深く印象付けてくれる。別れた妻に「あなたの最高傑作よ」と言わしめるほどのできであった。ただ、妻の表情は殺意が透けて見えるほどの嫉妬に満ちてはいたが...。
ミュージカル史に残るような見事なダンスパフォーマンス。それでも、彼を満足させることは決してないだろう。なぜならそれは彼の抱く理想とはまだ程遠いものだからだ。見る者の賛辞とはうらはらに、彼自身は理想に至る過程にすぎないと自らを責め、無能さを嘆き、自信を喪失しているに違いない。
何かを1つ表現すれば、理想の頂に至るどころか、克服すべき課題が堆く積み上がった新たな山に行く手を阻まれる...。しかし、真の表現者たちはその命が削られるようなゲームから降りようとしない。なぜか。次に表現すればさらに一歩理想に近づくと、彼らは確信しているからだ。だからこそ私たちは、驚きと感動に満ちた作品を、彼らから永遠に享受し続けることができる。
●私の心にまとわりつく、音楽と表現者たち
先日ロック歌手の忌野清志郎が亡くなったが、彼の声をはじめて聞いたのはデビュー間もない頃の'70年前後だったと思う。ラジオの深夜放送で音声が大きくなったり小さくなったりする韓国語放送の間を縫って聞こえてきたその声は鮮烈だった。曲は「ぼくの好きな先生」だったと記憶している。搾り出すようなあえいでいるような、突っ張った、一度聞けば忘れられない声だった。
清志郎は、歌手以外になれない、歌手をするために生まれてきたのだといっても過言ではない。我々に見せつけてくれたその生き方は、まさに表現者の名に恥じないものであった。彼の与えてくれた感動は必ず次の世代に引き継がれ、新たな"清志郎"を生むに違いない。
その頃にデビューした日本のミュージシャンを思いつくまま挙げてみよう。井上陽水、吉田拓郎、泉谷しげる、オフコース、チューリップ、郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹、山口百恵、沢田研二(ソロデビュー)、アリス、しばらくして荒井(松任谷)由美、アルフィー、サザンオールスターズ、YMO、ピンクレディーなど錚々たる面々が浮かんでくる。
自分の年齢のせいもあるとは思うが、こうした名前を見ていると「時代」が見えてくる。時代の空気を身にまとっているとでもいうのだろうか。その逆も言える。彼らが時代をまとったのではなく、私たちが「彼らという時代そのもの」をまとっていたのかもしれない。
つい最近、曲も歌手も全く知らなかったが、昨年の携帯ダウンロード1位の曲をじっくり聞いた。知らなくても今のところ別に困ることもないと思った。好きな音楽を決めつけているわけではない。私の心にヒットするのは、いまだにノンジャンル、国籍も問わない。最近のお気に入りは、今所属しているバンドのコンマス(コンサート・マスター:いい音楽を作るために色々と指示を出す人のこと)が取り上げた「SAMBA DE AMORE」(作曲:Arturo Sandoval)だ。とても美しいスロー・サンバである。サンドバルのフリューゲルホン(トランペットを1回り大きくしたような形。独特のくぐもった、柔らかい音を出す)が歌いまくっていて、心に届く音とは何なのかをわからせてくれる。最近良い音を聞いていないという方は是非お試しを。「ADIEMUS」も最近よく聞いている。人間の声の持つパワー、すなわち人間そのもののパワーを再認識させてくれる1枚だと思う。
ジャズがメインで聞いているが間口は結構広いという自覚がある。これからどのような音楽、ミュージシャンに出会うのかはわからないが、耳に入ってくる音には貪欲にアプローチし、聴く側として真摯に向き合っていこうと思っている。音そのものの中に作り手のすべてが込められているのだから。
2009年6月7日、札幌の北海道厚生年金会館で「原信夫とシャープス&フラッツファイナルコンサート2008-9」がある。ゲストはこてこての大阪弁で迫ってくる"浪速のジャズピアニスト"として知られる綾戸智恵。チケットは購入済みで、今、その日をわくわくしながら待っている。
そして今回もまた、シャープス&フラッツのメンバーでもあるあの彼のトランペットから聴衆を黙らせる音が出てくることを期待している。