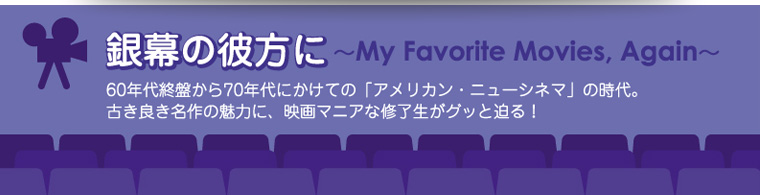Text by 村岡宏一(koichi Muraoka)
映像翻訳本科「実践コース」を2008年3月に終了。在学時は北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"であった。当年とって55歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
【作品解説】「男と女」(1966年)フランス―――当時まだ無名だった映画監督のクロード・ルルーシュと作曲家のフランシス・レイの名前を一躍世界に知らしめた作品です。第39回アカデミー賞外国語映画賞、脚本賞を獲得し、カンヌ映画祭でもグランプリ(現在のパルム・ドール)を獲得しました。
全編を通してセピア調のカラー映像とモノクローム映像が巧みに使い分けられており、的確なカメラワークで人間心理の多面性をあぶり出しています。
出演者の抑えた演技はとても自然でロマンチックですが、感傷に流されているということはありません。二人の現実の苦さと切なさの巧みな表現の中に心の揺れを感じつつ、私たちはゆっくりと静かに作品の世界へ引き込まれていきます。公開から40数年という時の隔たりを感じること無く、時代を超えて今の私たちの心に届く名作です。
この映画を語るとき、映像と音楽の絶妙なマッチングについて触れないわけにはいきません。映画を観たことがない方でも、あの有名な「♪ダバダバダ、ダバダバダ...♪」というメロディーはご存知かと思います。乾いた、そして少しけだるいスキャットがこの映画の印象をより深いものにしていることは確かです。
実はこの有名なテーマ曲の他にも、劇中には美しい曲がいくつも流れるのでぜひとも耳を傾けて下さい。特に、映画のラスト近く、ここは男性の視聴者にとってはかなり「イタイ」場面なのですが、二人が初めて愛を交わした後に流れる曲、「plus fort que nous」(邦題「あらがえないもの」)の切なさは胸を打ちます。
この作品以降、ルルーシュ&レイのコンビによる新作が次々に公開されました。「パリのめぐり逢い(1967)」、「白い恋人たち/グルノーブルの13日(1968)」、「流れ者(1970)」、「恋人たちのメロディー(1971)」、「愛と哀しみのボレロ(1981)(音楽担当はミシェル・ルグランも含む)」など、映画史に残るビッグタイトルが目白押しです。私たちの年代にとってはこのコンビによる作品群が一つのカテゴリーを形成していると言っても過言ではありません。
ある映画を観ると、心の中にそれにまつわる思い出という「部屋」が一つ増えます。そしてこれから新たに鑑賞する人たちにも次々とできていくことになるでしょう。映画音楽はさしずめ耳を通じて届けられる部屋の鍵ということになるでしょうか。
物語は、妻に自殺されたレーサー(ジャン=ルイ・トランティニアン)とスタントマン(ピエール・バルー)だった夫を撮影現場の事故により失ってしまった女性(アヌーク・エーメ)が、それぞれの子供を通わせる寄宿学校で知り合うところから始まります。二人は互いの境遇を理解し、思いは徐々に深くなっていくのですが...
■第18回:アート―-永久に語りかけるもの
ん? 何か臭う、焦げ臭い...、あ!しまった! と思って煙が立ち込めている台所に駆け込んでみると、ガスレンジにかけた鍋の中には、無残に焼け焦げたごちそうがこびりついている。肉じゃがになるはずだったのに。慌てて水を入れて、ひとしきり悔しがった後、うなだれた。(あぁ...これで今晩のメニューもおとといの夕食の再現だ...)。レトルトカレーと、お湯を注ぐだけでOKのコーンクリームスープ。手作り料理で心まで温まろうと考えていたときに、急にインスタントに変わってしまった無情感。食事をするというより餌を食べているような気になるのは私だけだろうか。
私の場合、こうなる原因ははっきりしていて、本かテレビかDVDだ。最近は妄想からうたた寝という困った原因も一つ加わったのだが、要するについでに時間つぶしでやっていたことのほうに、頭が勝手に優先順位をシフトさせてしまうのだ。並行して複数のタスクを処理するということが、段々と厄介になってきた。
ただ毎回そうなるわけでもない。「ついでのこと」が面白くなければ、周りはしっかり見渡せる。意識が覚醒しているからだ。つまり、私の意識は面白いと感じた何かに引き込まれた瞬間から現実の世界と切り離され、時間と空間を軽々と飛び超えていく。一瞬にして想像の世界の住人に変身してしまう。楽しみにしていた肉じゃがも黒こげになる。
私たちが生きているのは現実の世界だ。人、物、カネ、時間が入り乱れる戦場で生きながらえるためには、知識を蓄え、法律や経済の法則でがんじがらめになりながらも働き、結果を出し、自分の糧を得なくてはならない。決して避けることのできない他人との駆け引き、交渉、競い合い。押して引いて、なだめてすかして渡り合い、勝ったり負けたり...。
現実の世界では、それを毎日繰り返しているのだ。もしもそれが全てであれば、人間が齢を重ねるということは単にストレスを蓄え、疲弊するだけである。とても耐えられるものではない。だから私たちは想像の世界に飛ぶ。現実を一時的にでも強制的に切り離し、かろうじて精神のバランスを保っている。
想像力こそが人を生かしているのだ。
人間が地球上に登場して以来、想像力が、文化・文明を発展させてきたことは言うまでもない。素晴らしい芸術作品(アート)はその好例である。アートは人々に感動を与え、生きることの素晴らしさを直感的に実感させてくれる。
人類は「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」とも呼ばれる。「日々の労苦は、想像力を発揮して創造的活動を行うのに必要な糧を得るためにある、と思って耐えたい」、と以前どなたかがおっしゃっていたが、卓見である。あらゆる芸術(アート)価値は、創造者と鑑賞する側の作品を通した魂の共鳴によって増幅される。鑑賞する側の作品への思いやアプローチは千差万別でも、優れたアートは決して裏切ることなく答えを返してくれる。そしてそれが再び私たちの魂を揺さぶるのだ。肉じゃが(必要な糧)も、優れたアートを目の前にしては焦げついて然り、である(言い訳か...)。
映画のオープニング。主人公の女、アンヌ(アヌーク・エーメ)が娘に童話の「赤頭巾ちゃん」を語り聞かせている。アンヌは声色や動作に工夫を凝らして一生懸命伝えようとするのだが、うまく伝わらない。娘はそんな母親の熱演を無視し、「『青ひげ』のほうをお話しして」とせがむ。アンヌは再び「昔々...」と話し始める。カメラが引いてテーマ音楽が流れ、タイトルロールが始まった。
すでに私はレイ=ルルーシュが仕掛けた異世界に引きずり込まれている。
主人公はハンサムなレーサーと美人の未亡人、会話は洒落ていて、しぐさはスマート。"洗練"とはこういうことを言うのだろう。
難を言えば現実味が希薄な点だろうか。いや、だからこそこの映画は大人のメルヘン(童話)として、永遠に語り続けられることになるのだ。