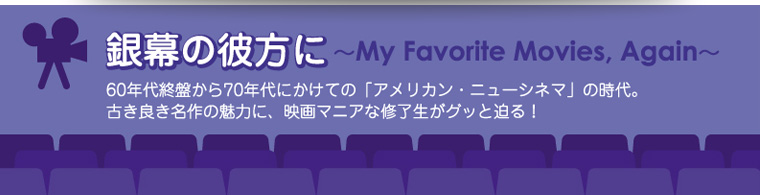Text by 村岡宏一(koichi Muraoka)
映像翻訳本科「実践コース」を2008年3月に終了。在学時は北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"であった。当年とって56歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
■第19回 シネマに魅せられし魂は永遠に輝く/「サンセット大通り」
(1950年)アメリカ
売れない脚本家ジョー・ギリス(ウィリアム・ホールデン)は自家用車のローンを滞納してしまう。その支払いを迫るクレジット会社の追跡を逃れるうちに、サンセット大通りに聳え立つ、寂れた豪邸に迷い込む。そこはかつてのサイレント時代の大物女優ノーマ・デズモンド(グロリア・スワンソン)の自宅だった。ノーマは銀幕への復帰を夢見て、自分をヒロインにした脚本を執筆しながら執事のマックス(エリッヒ・フォン・シュトロハイム)と暮らしている。
ノーマは彼が脚本家とわかると自分の脚本の手直しを依頼する。逃げ場のないジョーは衣食住を確保できるとあってこの仕事を引き受け住み込むことになるが、プライベートの時間も徐々に束縛されるようになり息苦しさを覚え始める。
ジョーはまるで情夫のような暮らしに辟易するが、そんな中で唯一の救いは同じ脚本家を夢見るベティ・シェーファー(ナンシー・オルソン)との密かな逢瀬だった。やがて二人の間に愛が芽生えてくる。しかし、ノーマもまたジョーを愛していたのだ。そしてその年の大晦日にある事件が起きる...。
本作は第23回アカデミー賞で12部門(作品、主演男優、主演女優、助演男優、助演女優、監督、脚本、撮影(白黒)、音楽、美術監督、美術装置、編集)にノミネートされるが、受賞は4部門(括弧内太字)にとどまった。
この年はジョセフ・L・マンキウィッツ監督、ベティ・デイヴィス主演によるバックステージものの最高傑作との呼び声も高い「イヴの総て」が主要部門をほぼ独占した。しかし、脚本賞受賞の事実が示すようにビリー・ワイルダー監督の執筆による脚本は素晴らしく、的を得た配役とストーリー展開の妙は我々の眼を最後までスクリーンに釘付けにしてしまう。アカデミー賞受賞数の寡少により作品の評価が減ぜられるものでは決してない。1989年創立のアメリカ国立フィルム登録簿に登録された最初の映画の中の1本であることも、その事実を裏付けるものである。
本作品を通じてワイルダー監督は、映画の持つ魅力や妖しさ、酷薄さ、そして夢、希望、金、欲を飲み込み、攪拌して、そのエキスを抽出するプロセスに関わるすべての人々にオマージュを捧げているかのようだと、私は感じている。なぜか。
次のような場面がある。ノーマが友人3人とブリッジに興じているのだが、その3人とはサイレント期の実際の大物俳優で、アンナ・Q・ニルソン、H・B・ワーナー、そしてバスター・キートンである。特にキートンは当時チャールズ・チャップリンやハロルド・ロイドと共に「世界三大喜劇王」の一人と称された稀代の役者だ。本作の中で「パス...パス」と言っている人物である。命がけのギャグを無表情かつスピーディーにこなして、往時は絶大な人気を博していた。日本の喜劇界の第一人者だった故益田喜頓(ますだ きーとん:北海道函館市生まれ 1993年没)の名前の由来が彼から来ているのはあまりに有名である。
ジョーはそのような彼らを「蝋人形」呼ばわりするのだが、"過去の人"となった彼らの存在を認めてくれるのはもはや同じ境遇の仲間しかおらず、そのことがノーマの実生活における孤独をさらに際立たせているのだ。短いが印象的なシーンで、本人と配役とがほとんど重なって見えるため、観る側はフィクションと現実の垣根が曖昧になり、不思議な緊張感をもたらしている。
ストーリーと現実が微妙に交錯しているのはそのシーンだけにとどまらない。映画監督のセシル・B・デミルが本人役で出演していて、本作中ではノーマとの関わり合いを避けようとしているという設定だ。しかし、実際にはサイレント時代にノーマ役のグロリア・スワンソン(ノーマ役)が主演する映画を何本も撮っている。
また、執事役のエリッヒ・フォン・シュトロハイムは、1920年代の名監督だ。ある場面でノーマのホームシアターで上映される「Queen Kelly」は、彼自身の監督作品なのだ。同作で彼は撮影途中にグロリア・スワンソンとトラブルを起こし、結局撮影中止にまで追い込まれ、彼の最後の作品となったといういわくつきの映画なのである。
スワンソン自身もこの時期は鳴かず飛ばずであった。とはいえサイレント時代にはあまりにも大物女優だったため、ワイルダー監督は本作への出演を引き受けてもらえないだろうと、ダメもとでオファーしたらしい。しかし、そのオファーを受けた彼女の仕事ぶりは圧倒的で、時代がかった物言いや立ち居振る舞いの尊大さからは、"人気女優であり続けることへの執念"が感じ取れる。鬼気迫るラスト・シーンは、映画史の伝説となったといっても過言ではない。
そんな女優、グロリア・スワンソンと、本作で演じたノーマ・デズモンドとの決定的な違いはそこにある。ノーマはサイレント時代のフィルムに浮かび上がる、若く美しい自分自身に固執し、その成功体験を捨てさることができなかった。観客の多くは彼女からとっくに背を向けているにもかかわらず、自分は永遠のスターと思い込んでいたことが、悲劇に拍車をかけることになる・・・・・・。
しかし現実のスワンソンは、演技者として確固たる自信を持っていた。年齢や容姿、体力の衰えなど関係ない――そう信じたからこそ、この作品への出演をOKしたのだ。燃え尽きぬ役者魂と共に、したたかな計算もあったに違いない。
スワンソン最後の出演映画となったのは「エアポート'75」(1974)である。私が彼女を実際のスクリーンで観たのはこの映画が最初で最後。77歳のグロリア・スワンソンが本人役で出演している。
映画の中でマネジャー役の女性に向かってこんなセリフを口にする。
「朝はいつも美しいものよ それがわかるには、あなたには10年早いわね
(Every morning is beautiful, you're just too young to know!」)
大女優、グロリア・スワンソンの面目躍如である。
1983年、老衰にて没する。享年86歳であった。