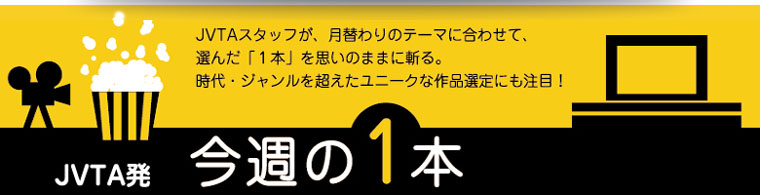vol.53 『恋におちて』 by 潮地愛子
3月のテーマ:出会い
ダブリンの街中で友達とコーヒーショップで暇つぶしをしていた時、What is life ? と聞かれたことがある。その時20代前半だった私は、その問いに即答することができなかった。たいして旨くもないコーヒーをすすりながらしばらく考えてみたけれど、気のきいた答えなどちっとも思い浮かばなかった。「人生なんて、ひとことで言い表せるもんじゃないよ」と私が言い訳をすると、彼女は言った。「そんなことないって、もっとシンプルだよ。私にとっては、Life is a choice.なの」
私よりいくつか年上の彼女がとてもオトナに思えたことを今でも覚えている。
そして、人生経験を重ねるにつれて、彼女の言ったLife is a choice. を実感することが多くなった。
人生には選択がつきまとう。私が今ここにいること。それは数々の選択の結果に他ならない。流されているつもりでも、思うようにいかなように見えても、結局は何気ない小さな選択の積み重ねの結果だったりするんじゃないか。そして、人生の選択につながる重要なファクターが「出会い」なのじゃないかと、この頃考えている。
誰と出会うか、何と出会うか。望んでいても、望んでいなくても。行き着く先が分からなくても。出会いは人生を左右する。ただ、右にいくか、左にいくかは、結局your choice なのだ。
何年か経って、彼女と再会した。当時、彼女は夫と離婚の話し合いを進めていた。彼は家を出て、新しい恋人と暮らしているということだった。結婚当初、彼はまだ学生だったので、生活を支えていたのは彼女だった。だが、彼が就職して生活が安定してから、彼女はずっと専業主婦だった。離婚となっては仕事を探さねばならない。彼女は言わなかったけれど、職探しは順調ではないようだった。シングルマザーで生活を支えていかなければならないことに苦労している様子がうかがえた。
もちろん夫婦の間にはいろんなことがあるのだろうし、私がとやかく言えることではないけれど、私は彼女の夫に対して腹立たしい気持ちでいっぱいだった。そんな私の心のうちを察したのか分からないが、彼女は言った。
「後悔してない。出会った頃、彼のことが本当に好きで、まるで『恋におちて』みたいだった。人生であんな思いを味わわせてくれた彼には、本当に感謝しているの」
そして、夫が新しい恋人に対してあの頃の私のような思いを抱いているんだろうなって、客観的には理解できるのよね、と言って彼女は笑った。
私は何も言えず、旨くもないコーヒーをすすりながら彼女の話を聞いていた。感覚を失ったかのように、何も感じることができなかった。そんなことを言えてしまう彼女に、ただただ圧倒された。
「恋におちて」をDVDレンタルショップで見かけて手にしたのは、彼女との再会を果たしてしばらくしてからだったと思う。
「恋におちて」はロバート・デ・ニーロ演じる妻子ある男フランクと、メリル・ストリープ演じる人妻モリーの恋物語だ。2人は偶然の出会いから恋に落ち、プラトニックな関係を続けていく。だが、結局はほころびが見えていたそれぞれの結婚生活には終止符が打たれる。
そして映画は、お互いを忘れられない2人の再会によりハッピー・エンドで終わる。
確かに、相手を思い続ける2人の愛は純粋で美しいのかもしれない。でも、私はこの映画を好きにはなれなかった。多分それは、愛している相手が他の人に心を奪われていくモリーの夫やフランクの妻の哀しさに、胸を打たれてしまうからなのだと思う。もちろん人の気持ちは無理に変えることはできないけれど、この映画で描かれる純粋で美しいとされる愛が、去られた者に残すのは、時に残酷で醜いものだったりするのではないか。
それでもすべては結局、それぞれの選択の結果に過ぎないのかもしれない。残酷で醜いものを残されてしまうことも含めて。いや、だけど・・・。
まだまだ、私が未熟なのだろうと思う。もっといくつもの選択を重ねて、いつかこの映画を観たら、異なる想いを抱くことができるのかもしれない。
彼女とは、あれ以来会っていない。でも、たいして旨くもないコーヒーをすする羽目になるたび、彼女の言葉を思い出す。そして、彼女がどこかで幸せにやっていることを願うのだ。
─────────────────────────────────
『恋におちて』
出演:ロバート・デ・ニーロ、メリル・ストリープ
監督:ウール・グロスバード
製作:マーヴィン・ワース
製作年:1984年
製作国:アメリカ
─────────────────────────────────