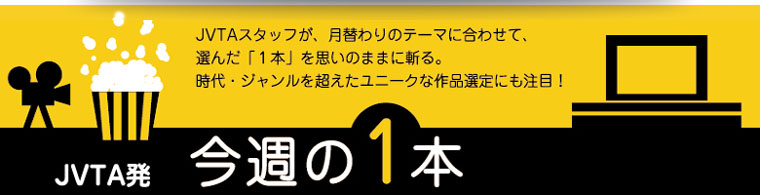9月のテーマ:クセ
原題「Capitalism: A Love Story」。癖の強い、でも一度観たら癖になる作品を撮り続けるマイケル・ムーア監督の待望の最新作だ。「世の中の悪事と不条理のすべては、元をたどればすべて資本主義が原因である」という偏った意見を持っている私は、10月2日の全米公開が待ちきれず先行公開に出かけた。
「華氏911」ではブッシュ前大統領を痛烈に批判。前作「シッコ」ではアメリカの医療制度とアメリカ国民の現状を悲劇的に描いたムーア監督。そんな彼が今回テーマとして選んだのは、なんと資本主義。とてつもなく大きな敵と戦う気らしい。
サブプライムローンを組まされ支払が滞った家族が、担保である家を取り上げられるシーンから始まり、昨年から続く金融危機と世界不況の原因を分かりやすく解説。アメリカ型の市場主義経済の崩壊と資本主義の弊害を映し出す。
他の国では当たり前に存在する国民健康保険制度すら存在しない、超自由資本主義経済のアメリカ。教育も健康も、すべてがビジネス。他人がどうなろうがおかまいなし。そんな弱肉強食・利益至上主義の現状と、古きよきアメリカを比べ、その変遷を追っていく。
大統領選挙の2ヶ月前に突如発生した今回の金融危機。偶然にしては出来すぎていると眉をひそめる有識者たちは、すべては巧妙に仕組まれた詐欺だと言い放つ。事実、ウォール街のCEOたちはこの金融危機で大儲けしている。
たくさんの興味深い映像の中に、印象的なシーンがあった。テーブルの上においてあるパイを、子犬が必死にジャンプして取ろうとするのだ。ジャンプすればパイは見えるけど、手は届かない。どんなに力いっぱいジャンプしてもパイにはありつけず、椅子に座った人間が笑いながらパイを食べている。
周知の事実だが、世界の99%の富は、1%の金持ちによって所有されている。富める者がさらに富むように作られた資本主義システムでは、どんなに頑張ってもその1%にはなれない。しかし「アメリカン・ドリーム」というありもしない幻想を夢見せられて、貧しい者は苦しい生活に耐え続ける。
それはすべて、富裕層が描いたシナリオ通り。無慈悲にそしてスマートに欲しい物を奪っていくウォール街のエリートたちにはある意味、感嘆するが、改めて彼らの論理を説明されると、その強欲で利己的な言動にはヘドが出る。本来システムというものは、人々のために存在するべきものだ。しかし今は、「経済」というシステム自体が大きく育ちすぎて、それを維持するために、人々が犠牲になっている。
そして最後にムーア監督は観客に、この現状を変える力を貸してほしいと訴える。民主主義では誰もが平等に1票の投票権を持っている。資本主義のひずみが表面化し、人々が不平等に気づき初めた今こそ、民主主義の本当の力を見せ、我々の権利を叫ぶのだと。
日本では今年12月から限定公開、10年1月から全国拡大公開される。
──────────────────────────────────
『キャピタリズム~マネーは踊る~』
監督:マイケル・ムーア
製作年:2009年
製作国:アメリカ
──────────────────────────────────
10月のテーマ:クセ
ひさしぶりに音楽モノをスクリーンで観た。
『扉をたたく人』
第4回UNHCR難民映画祭のクロージングを飾った作品だ。よかった。いい意味でばっさり裏切られて、これがまた実に感動した。
私は音楽モノ作品には、無条件に感動してしまうクセ(?)がある。
ぱっと思いつくものでも、『4分間のピアニスト』『戦場のピアニスト』『海の上のピアニスト』(やっぱり、ピアノ系の邦題って「ほにゃららのピアニスト」ってなってしまうことについて【余談】)...ほらね、感動してたでしょ。
ラフマニノフの3番がなんたるかも知らないくせに、思わず『シャイン』のサントラ買っちゃうし、ゴスペル初心者のくせに、やっぱりソウルに響くんだよ、これ、と、『天使にラブ・ソングを』のOH!HAPPY DAYを練習しちゃうし、『スウィングガールズ』だって、(今ではカワイイけど)上野樹里含む微妙な女子高生で十分感動してたし。そういう感じ。
繰り返される単調な日常において、ひょんなことから主人公が音楽や楽器に出会い、のめりこんでいく。今まで周囲のことに無感動だったような人間も、音楽によって人生が大いに彩られたり、ちょっとやそっとの困難だって、奇跡のガッツで乗り越えちゃったり。NO MUSIC, NO LIFE精神。人が何かに夢中になり、我を忘れてのめりこんでいく姿って単純に引きつけられてしまう。
専門家が聞けば、その演奏はそれほどミラクルでないかもしれないし、「このシーンは、替え玉か?」などと考えてしまうこともしばしばあるけど。それでも、音楽モノ、楽器モノは奏でられる音楽と、主人公の感情の昂ぶりとでグルーブしまくっちゃって。これまたどんなダイアログを並べられるより、心打つものがあったりするわけで。なんとも分かりやすくて、好きだ。
さて。
『扉をたたく人』は音楽モノでありながら、中盤から殆ど演奏シーンがでてこない。それがまた、音楽が人生にとって、どれほど価値あるものとなりうるかをみせている素晴らしい構成だ。
主人公の大学教授ウォルターがシリアからの移民少年タリクと出会うまでは物語は実に単調。その後、ジャンベ(アフリカン・ドラム)が奏でるアフリカンビート(3拍子)にのって、ストーリーは一気に盛り上がる。しかし二人の心が通い合うがいなや、不法滞在を理由にタリクは拘束されてしまう。そこからはジャンベの音色どころか、劇中音楽すら、殆ど出てこない。
タレクは、ガラス越しに訴える。
「自由に生きて、自由に自分の音楽を奏でたい」
生きることを奪われた青年に、本当に生きるとは何かを教えられる、ウォルター。そして音楽を奪われたことの、苦しさがそれこそ痛いくらいに伝わる。さっきまで心地よく響き渡っていた、あのジャンベの音色に対する枯渇感を観客は感じずにいられない。
自由の国、アメリカ。拘置所の近くにはその自由を謳歌するようなグラフィティアート。壁をへだてた向こうでは、人を番号で管理する自由とはかけ離れた世界がある。明日の居所さえ保証されない。家族さえ事前に知ることが出来ない。その扱いは宅配便の管理以下だ。ウォルターがタリクを救うため依頼したのはアラブ系弁護士。叔父も強制送還された経験を持つというアラブ系の彼も、高価なスーツを身にまとったニューヨーク出身、完全なアメリカ人だ。ベストは尽くすと一蹴された依頼人は、もはやなす術もない。だが現在のアメリカでは、その言葉にすがるしかないのだ。
不法滞在を擁護するつもりはさらさらない。ただ、9.11を経験したアメリカは、明らかになにか大事なものを失ったと思わざるをえない。
Broadway Lafayette ST.のプラットホームでジャンベを打ちならすラストシーン。次第に近づき重なるもうひとつの3拍子。ジャンベの音までも飲み込むそれは、ホームに滑り込む地下鉄の音。
ノーベル平和賞を受賞した大統領を擁すこの国は、この先、この国に生きる人全てに、自由と平和を保証してくれるのだろうか。
上野樹里といえば、『のだめカンタービレ』。原作は、いよいよ連載最終回!一大クラシックブームを巻き起こしたこの作品も、終わってしまうのか... ( ̄д ̄)エー。単行本出るまでほんとに待ちきれない...。
─────────────────────────────────
『扉をたたく人』
製作年:2007年
製作国:アメリカ
監督:トム・マッカーシー
出演:リチャード・ジェンキンス
(2009年アカデミー賞主演男優賞ノミネート)
ハーズ・スレイマン、ヒアム・アッバス
─────────────────────────────────
10月のテーマ:クセ
いつの間にやらそれなりの大人になってからというもの、事あるごとに思い出し、こいつはよく言ったものだね、と感心するようになったのが「三つ子の魂百まで」ということわざです。
幼児教育に臨床心理学に性格判断、果ては宗教理論まで、様々な文脈において、こう言ってよければ実に好き勝手な解釈で援用されてきたこのことわざの、誰が言い出したのかはさておくとして、三つ子に魂があることをさらりと前提としている慧眼には、ひとまず感服しないわけにはいきません。
考えてみると、私たちは自分よりむしろ他人について「三つ子の魂百まで」という感慨を抱く機会が多いのではないでしょうか。
相手が子供にしろ大人にしろ、なぜか変わらない好みや、いつ始まったのか分からない性癖、自然に選んでしまう特定の行動パターンや思考パターンといった、その人らしさを示すある種の"印"に触れた時、私たちは「百まで」消えることなく続くであろう何かの存在をぼんやりと感じるわけです。
その時に私が思い浮かべる魂は、それこそ個人的な趣味(癖?)に過ぎないのでしょうが、必ずしもスピリチュアル的な、輪廻転生する魂ではありません。
どちらかというと後にも先にもなく1回完結で、その人を他の人と最終的に隔てる、似通って見えても実は交換不可能な何かのような気がします。
ただ、もちろん私はそんな魂の姿を見たことなどなく、実際には、幼稚園に通う2人の甥がじゃれ合ったりケンカしたりしている様子や『恋愛日記』でシャルル・デネールがモンペリエのデパートを歩く女性の後をつける場面を見て、「三つ子の魂百までか...」とひとりごちているばかりなのですが。
フランソワ・トリュフォーが女性の脚の魅力に取り憑かれた中年男の数奇な生涯を描いた『恋愛日記』において、シャルル・デネール演じるベルトランが女性の脚になぜそれほど執着するに至ったのかは、ついに説明されることはありません。
多くの女性を愛し、多くの女性から愛されたベルトランの人生を、映画は彼の性癖に基づく行動だけに焦点を当てて映し出していくのです。
モーリス・ジョーベールによる優雅で軽やかな室内楽をバックに、『恋愛日記』はベルトランの葬儀のシーンから始まります。
参列者がすべて女性のみという、異様であり、楽園的でもあるこの場面のムードは、作品の主旋律となってラストシーンまで途切れることなく流れ続けるのですが、見る者はやがて、おとぎ話と悪夢の区別がつかなくなるかのような、奇妙な時間に出会うことになるでしょう。
個性豊かな曲線を描いて大地に立つ2本の脚。そんな脚を持った生き物としてしか女性を愛せないベルトランの生活を、トリュフォーは嘲笑することなく、生真面目な解剖医のような手つきで画面に収めていきます。
それは自らの性癖に振り回されて生きるしかなかったベルトランの、ユーモラスに思えるほど真剣で矛盾に満ちた"魂"に触れる、唯一の方法だったのかもしれません。
当時学生だった私がこの作品を初めて見た時に強烈に印象に残ったのは、無邪気に微笑むブリジット・フォッセーのえくぼと、スローモーションで描かれたある1シーンでした。
ベルトランの回想とも白昼夢ともつかないその場面では、春服を着た何十人もの女性が地下鉄の出口の階段を一斉に駆け上がる姿が映し出されていました。
どこか『トリュフォーの思春期』の冒頭の、子供たちがティエールの町の坂道を一斉に駆け下りる場面をほうふつとさせるシーンです。
その陽射しと躍動感と歓喜があふれかえるような画面は、きっとトリュフォーが映画に残した"印"なのだと思います。
─────────────────────────────────
『恋愛日記』
監督:フランソワ・トリュフォー
脚本:フランソワ・トリュフォーほか
音楽:モーリス・ジョーベール
出演:シャルル・デネール、ブリジット・フォッセー、ナタリー・バイ、
レスリー・キャロン、ネリー・ボルジョーほか
製作国:フランス
製作年:1977年
─────────────────────────────────