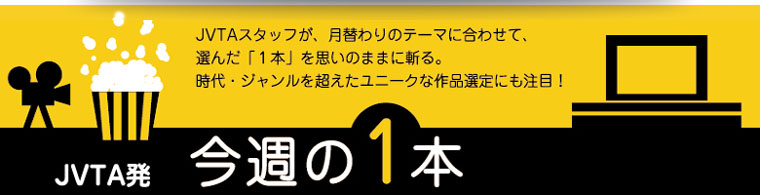10月のテーマ:クセ
いつの間にやらそれなりの大人になってからというもの、事あるごとに思い出し、こいつはよく言ったものだね、と感心するようになったのが「三つ子の魂百まで」ということわざです。
幼児教育に臨床心理学に性格判断、果ては宗教理論まで、様々な文脈において、こう言ってよければ実に好き勝手な解釈で援用されてきたこのことわざの、誰が言い出したのかはさておくとして、三つ子に魂があることをさらりと前提としている慧眼には、ひとまず感服しないわけにはいきません。
考えてみると、私たちは自分よりむしろ他人について「三つ子の魂百まで」という感慨を抱く機会が多いのではないでしょうか。
相手が子供にしろ大人にしろ、なぜか変わらない好みや、いつ始まったのか分からない性癖、自然に選んでしまう特定の行動パターンや思考パターンといった、その人らしさを示すある種の"印"に触れた時、私たちは「百まで」消えることなく続くであろう何かの存在をぼんやりと感じるわけです。
その時に私が思い浮かべる魂は、それこそ個人的な趣味(癖?)に過ぎないのでしょうが、必ずしもスピリチュアル的な、輪廻転生する魂ではありません。
どちらかというと後にも先にもなく1回完結で、その人を他の人と最終的に隔てる、似通って見えても実は交換不可能な何かのような気がします。
ただ、もちろん私はそんな魂の姿を見たことなどなく、実際には、幼稚園に通う2人の甥がじゃれ合ったりケンカしたりしている様子や『恋愛日記』でシャルル・デネールがモンペリエのデパートを歩く女性の後をつける場面を見て、「三つ子の魂百までか...」とひとりごちているばかりなのですが。
フランソワ・トリュフォーが女性の脚の魅力に取り憑かれた中年男の数奇な生涯を描いた『恋愛日記』において、シャルル・デネール演じるベルトランが女性の脚になぜそれほど執着するに至ったのかは、ついに説明されることはありません。
多くの女性を愛し、多くの女性から愛されたベルトランの人生を、映画は彼の性癖に基づく行動だけに焦点を当てて映し出していくのです。
モーリス・ジョーベールによる優雅で軽やかな室内楽をバックに、『恋愛日記』はベルトランの葬儀のシーンから始まります。
参列者がすべて女性のみという、異様であり、楽園的でもあるこの場面のムードは、作品の主旋律となってラストシーンまで途切れることなく流れ続けるのですが、見る者はやがて、おとぎ話と悪夢の区別がつかなくなるかのような、奇妙な時間に出会うことになるでしょう。
個性豊かな曲線を描いて大地に立つ2本の脚。そんな脚を持った生き物としてしか女性を愛せないベルトランの生活を、トリュフォーは嘲笑することなく、生真面目な解剖医のような手つきで画面に収めていきます。
それは自らの性癖に振り回されて生きるしかなかったベルトランの、ユーモラスに思えるほど真剣で矛盾に満ちた"魂"に触れる、唯一の方法だったのかもしれません。
当時学生だった私がこの作品を初めて見た時に強烈に印象に残ったのは、無邪気に微笑むブリジット・フォッセーのえくぼと、スローモーションで描かれたある1シーンでした。
ベルトランの回想とも白昼夢ともつかないその場面では、春服を着た何十人もの女性が地下鉄の出口の階段を一斉に駆け上がる姿が映し出されていました。
どこか『トリュフォーの思春期』の冒頭の、子供たちがティエールの町の坂道を一斉に駆け下りる場面をほうふつとさせるシーンです。
その陽射しと躍動感と歓喜があふれかえるような画面は、きっとトリュフォーが映画に残した"印"なのだと思います。
─────────────────────────────────
『恋愛日記』
監督:フランソワ・トリュフォー
脚本:フランソワ・トリュフォーほか
音楽:モーリス・ジョーベール
出演:シャルル・デネール、ブリジット・フォッセー、ナタリー・バイ、
レスリー・キャロン、ネリー・ボルジョーほか
製作国:フランス
製作年:1977年
─────────────────────────────────