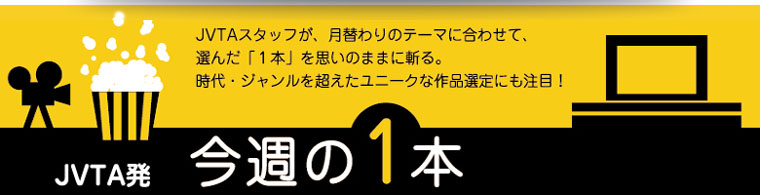vol.107 『マリー・アントワネット』 by 杉田洋子
6月のテーマ:半分
最近、古いフランス映画を続けて観た影響か、きれいで可愛いものが見たくなって、遅ればせながら鑑賞してみたのがこの作品だ。
公開当初、内容についてあまり絶賛の声を聞いていなかったので、目の保養と思って見たのだが、思った以上に引きこまれてしまった。1人の女性として、共感できたり、尊敬できる部分が多々あったからだ。
恥ずかしながらマリー・アントワネットについて私が知っていたことと言えば、"パンがなければお菓子を食べればいいじゃない"という有名な文句と、ぜいたく三昧で国民の怒りを買った、ギロチンになったということぐらい。
"パンがなければ~"と言ったのが、実は彼女じゃないということも知らなかった。
映画の中での彼女は、ポジティブで、正直で、個人的には好感が持てた。若くして他国の王室に嫁ぎ、あほらしくなるような形式主義に違和感や空しさを覚え、自分の直感を信じ、はっきりと異を唱える。
一方、夫であるルイ16世は性的機能に問題をかかえており、女性としては満たされない日々が続いていた。応えてもらえない空しさと、ご懐妊を待つ周囲からのプレッシャー。自分の存在意義を問いただしたくなるような板挟みの中で、ある時を境に彼女は吹っ切れる。そしてようやく、私たちの多くが知っている、ファッションやパーティー、ギャンブルに傾倒した散在生活が始まる。
"いいじゃないか"。それが私の感想だった。暗くなって、絶望して、下を向いてるより、アルコールにおぼれて体を壊すより。もちろん限度はあるだろうし、周りにも迷惑かけただろう。けれど、明るく前向きに乗り切る方法を見つけたのなら、それでいいじゃないかと。
完全に満たされた状態なんて人生に何度訪れるだろうか。訪れたとしても、それは瞬間的ないくつかの点にすぎないだろう。あとの大半はどっちかこっちか(これって方言だと指摘されたのですが、二兎は得られませんよ、どっちか良ければどっちか悪いよ、っていう意味で使っています)で、それでもよい方に支えられて、何とか前を見て歩いているのではないか。誰だって。ただ彼女が王妃で、住処がお城だっただけのこと。
それでも夫のそばを離れず、ようやく恵まれた子どもを心から愛し、毅然とした態度で生き抜く姿は(もちろん、この映画の中での彼女だけれど)、女性として尊敬できた。
史実の忠実な再現というよりは、1人の女性を描いたドラマであることは、制作側も明らかにしていることだが、すべての行動にきっかけや原因があるとすれば、むしろ自然なこととして受け入れられる。単なる正当化じゃなく、これなら合点がゆくな、と。当時の民衆に見えていたのも、都合よく解釈した、彼女のほんの半面(もないか)でしかなかったはずだ。
お金や地位があっても孤独、というのは、よく取り上げられるテーマだけれど、この作品は、現代の一般女性の心にも通じる普遍的な心理を描いた、女性監督ならではの作品だと思う。
あ、もちろん、ファッションや色とりどりのお菓子に小物まで、視覚的にも大変楽しめました。
─────────────────────────────────
『マリー・アントワネット』
監督:ソフィア・コッポラ
出演:キルティン・ダンスト、ジェイソン・シュワルツマン他
製作国:アメリカ
製作年:2006年
─────────────────────────────────