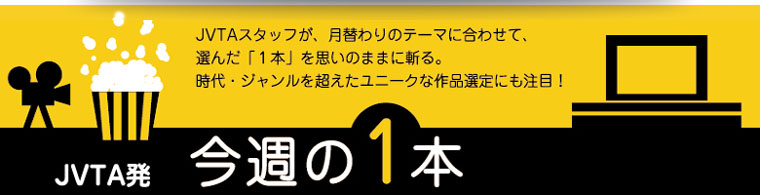vol.109 『セントラル・ステーション』 by 藤田奈緒
7月のテーマ:手紙
つい1ヵ月ほど前のことだが、何ともこっ恥ずかしい再会をした。学生時代の友人が、すごく面白いものを見つけたから今度見せる!と言って持ってきてくれたのが、なんと14年前に私自身が書いた手紙だったのだ。その夏休み、私は実家のある名古屋に帰省していた。それほど暇を持て余していたのか、それともそれほど純な学生だったのか、いずれにせよ、私は友人宛てに手紙を書いたらしい。
丁寧に半分に折られた便箋は、小ぎれいな字で埋められているのが透けて見え、期待は高まった。しかし14年ぶりに開いてみてガックリ。あまりにも、たわいなさ過ぎる...。夏休みも半ばを過ぎたが未だ課題に手をつけられていないこと、共通の友人に彼氏ができたらしいこと、名古屋にようやくハードロックカフェができたこと。これらがさも大事件かのようにエクスクラメーション・マーク付きで書き連ねられていたのだ。(ちなみに名古屋のハードロックカフェは現在は閉店...寂しい)大爆笑する友人を前に、私は気まずさをごまかしながらひっそりと便箋を封筒に戻すしかなかった。
しかし思う。手紙というものは、たとえ殴り書きでも、たとえどんなに短い文章でも、書き手に伝えたい思いがあって、それを受け取る人がいれば、必ず意味を持つ。大人になった今、苦笑してしまうような内容だとしても、大学生の私にとっては、それが伝えたいことであり、大学生の友人にとっては受け取る価値がある情報だった。だからこそ14年の時を経てもその手紙は存在し、今またこうして私たちを笑わせてくれ、あの頃へと引き戻してくれるのだ。
ブラジル、リオデジャネイロの中央駅(セントラル・ステーション)で小さな机と椅子を出し、代筆業を営む元教師のドーラ。彼女の元には連日、さまざまな現実を背負った人たちがやって来る。何年も会っていない家族、離ればなれになってしまった恋人、自分で相手に伝えたいけれど伝える術のない人たちの思いを、ドーラは代わりに言葉にして手紙にしたためる。過去の経験から人間不信に陥っていた彼女がこの仕事をしていたのは、人助けのためなんかではなく、ただ生きていくためだった。1日書き続けたせっかくの手紙を投函することもなく、時には笑いものにして破り捨てる日々。みんなの思いが相手に伝わることはなかった。
だが1人の少年との出会いが、乾ききったドーラの生活に変化を与える。母親を事故で亡くし、行くあてもなく駅をさまようジョズエを見かね、不本意ながらも一緒に父親探しの旅に出ることになったのだ。純粋無垢な少年と時を過ごし心を通わせていくうちに、頑なだったドーラは癒されていく自分に気づく。何年も諦めていたこと、人に対して心を開く勇気をジョズエからもらったのだ。たどり着いた目的の村で、ドーラは再び机を出しペンを取った。そして村人たちの思いをかみ締めながら書いた手紙を、破り捨てることなくきちんと投函するのだった。
その後ジョズエと別れたドーラは、バスに乗ってどこへ行っただろう? きっとセントラル・ステーションではないはずだ。今度は自分自身の思いを自分の口で伝えるため、大事な人の元へ向かったに違いない、そう思う。
─────────────────────────────────
『セントラル・ステーション』
監督:ヴァルテル・サレス
出演:フェルナンダ・モンテネグロ、ヴィニシウス・デ・オリヴェイラ
製作国:ブラジル
製作年:1998年
─────────────────────────────────