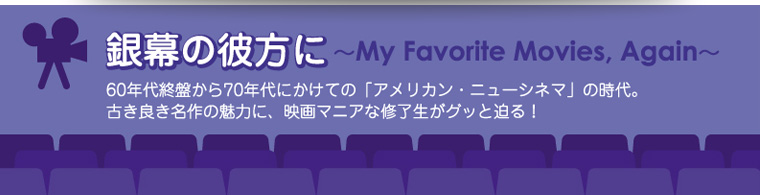第20回 「キング・コング」(1933年)と「アバター」(2009年)
Text by 村岡宏一(Koichi Muraoka)
映像翻訳本科「実践コース」を2008年3月に終了。在学時は北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"であった。当年とって56歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
■第20回 映像テクノロジーの進化は何をもたらすのか?/「キング・コング」(1933年 アメリカ)と「アバター」(2009年 アメリカ)
今日は、旭川市にある某シネ・コンのメンズ・デー。降りしきる雪の中を1時間近くかけてやってきた。駐車場は除雪がまだ手付かずで、運転席から足を降ろすと膝下近くまで埋まってしまったが、この時期の北海道では当たり前のことで、そんなことは誰も苦にせずに行動する。とはいっても、苦労して観に来たのに期待した結果が得られなかったときの落胆は雪のない時期より大きいのは確かだ。今日は果たしてどうであろうか。
通常のメンズ・デーは男性が1000円で映画鑑賞をすることができる。しかし今日はジェームス・キャメロン監督12年ぶりの新作「アバター」の3D版を鑑賞しようと決めていたので、それにプラス300円が必要となる。1300円で入場券を購入し入場口まで進むと入場券と交換に係員の女性が3D用のメガネを渡してくれた。がっちりとした固いゴムのようなフレームで作られており、レンズには薄く色が付いている。普通のメガネをかけていてもその上に装着できる。重さは軽いと言って良いのか、普通のメガネよりはわずかに重いような気がするが鑑賞にはほとんど差しさわりの無い程度だ。
場内の照明が落ち、予告編が始まり何本か終了した後でスクリーンに「メガネをかけてください」と指示が出る。その後の予告編はディズニーのアニメーション映画の3D版だった。恐らく3Dの感覚に慣れさせる意味合いもあるのだろう。
ファンファーレと共におなじみの21世紀フォックスのロゴがスクリーンいっぱいに立ち上がるが、すでにここから立体映像だ。
そして本編が始まったが...。
小学生の頃、NHK教育テレビで不定期に「劇映画」という番組があった(と記憶している)。文字通り映画作品をテレビで放映していたのだが、ほぼ半世紀も前の時代においては、推察だが、恐らくソフト数が足りなかったか、あるいは著作権の問題で放映できない作品が多かったのか、同じ作品を何度も見たような覚えがある。
SFX映画の原点といわれる1933年版「キング・コング」もその中の1本だった。冬休みのたびに見た記憶がある。ただ不思議に見飽きるということがなかった。最後に見てから40年以上経っているわけだがいくつかの印象的なシーンは今でも目に焼き付いている。
恐竜プテラノドンとの格闘シーン、ニューヨークの劇場でコングが見世物となっていたときに、新聞記者が次々と焚いたカメラのフラッシュに驚き、咆哮を上げて渾身の力を込め自分を縛り上げていた鎖を引きちぎるシーン、さらに、美女を小脇に抱えエンパイアステートビルを登っていく、あの、あまりにも有名なシーンなどなど。中でもコングに機銃掃射を浴びせる戦闘機の主翼の羽根が複葉(2枚)であったことがとても珍しくて目を凝らしていたのを今でも覚えている。
今回、1933年版「キング・コング」のコラムを書くために資料を調べていたところ、今まで全く知らなかった事実を一つ確認できた。撮影にあたり人間が着ぐるみを着用しコングを演じたのではなく、身長わずか46センチメートルの精巧なミニチュアを使い、「ストップモーション・アニメーション手法(ほんの少しずつ人形を動かしながら1コマずつ撮影しそれをつなぎ合わせる手法。ノートの片隅に少しずつずらして描いた人間をパラパラと素早くめくると動いているように見えるあれである)」で全ての登場シーンを撮影したというのだ。
ハリウッド初のSFXアーティスト、ウィリス・H・オブライエンの気の遠くなるような根気と努力により、ミニチュアのコングに見事に生命が吹き込まれた。今でもコングの表情や動きのリアリティーには感嘆してしまう。当時の彼の才能とパワーには惜しみない賛辞を贈るしかない。
その「キング・コング」から60年、1990年代になるとCGによる恐竜映画「ジュラシックパーク」が公開された。まさに自分たちの目前で生きているとしか思えない恐竜たちの動きと迫力に、世界中の観客は度肝を抜かれたものだ。ハリウッドの中で連綿として受け継がれてきた特殊撮影技術の革命的向上であり、それはまた全く新しい映像時代の幕開けでもあった。
'97年に公開されたジェームス・キャメロン監督の「タイタニック」でもCG技術が巧みに活かされており、作品の内容とも相俟ってアカデミー賞の各部門賞総なめにする。だがこの時点で、彼が次回作公開までに12年の歳月を要し(ドキュメンタリー作品等を除く)、しかもそれが3Dであることなどいったい誰が想像できただろう。
「アバター」に話を戻そう。この映画の印象をひと言で言えば「すべてが整っている」。ありえない創造物の世界と計算されつくした裏づけ。それらが立体画像を通じて私たちの目前に差し出される。鑑賞している私たちが3D効果によって浮遊させられた位置から見える画面の奥行き。谷底の高さにヒヤッとし、こちらに飛んでくる弾丸の薬莢を思わずよけてしまう。ストーリーの運びもテンポよく、主人公の愛と苦悩、人間の欲望の愚かさ、そして本当に大切なこととは何かを、私たちに問いかけてくる。興行収入も「タイタニック」の記録を抜いて歴代第1位になったようである。
ではこれからの映画作りの主流が3Dになるかといえば、そう単純に事は運ばないだろう。あくまで映画表現の一手段と捉えるのが順当ではないだろうか。アクション系やファンタジー系などのジャンルにおいては有効な表現手段になるのは確実である。バーチャルリアリティを限りなくリアルに近づけるための技術革新と努力は世界中のどこかで今も続けられているはずだし、それはそれで期待していい。
ただ、ここで今一度考えなくてはいけないことがある。「私たちはなぜ映画館に足を運ぶのだろうか」という素朴な問いへの答えについてだ。
私たちはスクリーンに映し出された1秒間24コマの動く画像と音、音楽を聴きながら様々なことを想像する。シーンに応じて、絶え間なく、いくつもの感情が生まれては消える。この心地よさこそ、劇場での映画鑑賞の本質だと私は考えている。映像技術が進化し、過剰なまでに至れり尽くせりのワザで製作者の計算通りに視覚と聴覚を刺激されるだけの作品で、本質的な感動を味わえるのだろうか・・・。
ここである言葉を思い出した。テレビの黎明期にジャーナリストの大宅壮一氏が唱えた「一億総白痴化」という言葉である。テレビというメディアは非常に低俗でテレビばかり見ていると人間の思考力や想像力を低下させてしまう、というような意味だ。だが、テレビ放送が始まって半世紀以上が経つが、どうやら日本は存続し、1億人が「白痴化」した気配はない(読書量の低下や家族間の会話の減少を生み出した原因の一つにはなっているかもしれないが)。人間の脳の力はまだまだ未解明な部分がほとんどだそうである。この豆腐のように柔らかい器官はなかなかしたたかなようだ。私の心配も杞憂に終わるのかもしれない。
キング・コングが日本映画に登場しているのをご存知だろうか。1962年、東宝創立30周年記念作品として、日本を代表する怪獣「ゴジラ」と戦わせた「キングコング対ゴジラ」と、その流れで製作された「キングコングの逆襲」である。前作は「キング・コング」以来不遇を囲っていたウィリス・オブライエンの企画書「キング・コング対ガルガンチュア」が、流れ流れて日本にたどり着き東宝が権利を購入したのだという。私は残念ながらスクリーンで見ていないが、小学生の頃は東宝特撮怪獣映画を兄弟3人でよく観に行ったものである。
今から考えれば当時の特撮技術は手作りの苦労が画面を通じて滲み出てくるような、お粗末な代物だったはずである。しかし、撮影所に設置したプールと巨大な板に書割の灰色空の下、海に見立てた水がゆっくりと盛り上がり白い波が立ち、やがて着ぐるみのゴジラがゆっくりと現われ大きく咆えた瞬間の興奮を、私は未だに忘れることができない。