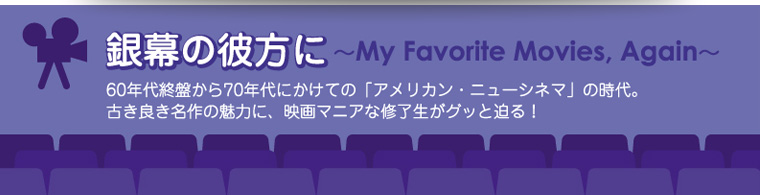Text by 村岡宏一(Koichi Muraoka)
映像翻訳本科「実践コース」を2008年3月に終了。在学時は北海道・札幌市から毎週土曜日"飛行機通学"であった。当年とって54歳。映画、特に人生に大きな影響を与えてくれた、60年代終盤から70年代にかけての「アメリカン・ニューシネマ」をこよなく愛す。
今回は70年代の邦画にスポットをあて、その魅力について論じている。
【作品解説】 70年代当時は邦画もよく見ていました。独立系のはしりでもあったアート・シアター・ギルド(略称ATG)配給の作品などは、社名の通り非常に芸術性が高く難解でしたが、監督それぞれの個性が極めて色濃く映像に反映されていました。当時の作品は、鑑賞していると何か映像がこちらに挑んでくるような思いにさせられ、常に緊張を強いられたのですが、こちらもその挑戦を受けてたつような気持ちで見ていた記憶があります。
そんなATGの作品の紹介は次の機会に譲るとして、今回は「青春の蹉跌」という東宝配給の作品を取り上げました。この映画は私が学生時代に見た邦画の中で最も印象に残っている作品の一つです。第1回芥川賞受賞作家、石川達三の同名小説を映画化した作品で、監督は当時の日活ロマンポルノで名を馳せていた神代辰巳(クマシロタツミ)です。彼はこの作品で一般映画の監督としてデビューを果たしました。彼の代表作の1本と言えるでしょう。
主演は萩原健一(通称「ショーケン」)と桃井かおり(某クレジットローンのCMに竹中直人と出演している女優さん、と言ったらおわかりでしょうか...)ですが、この2人を見ていると、当時の空気が孕んでいた倦怠感と諦観を感じ取れます。撮影時はそれぞれ24歳と22歳と年齢的にはまだ若手でしたが、その存在感と演技力はすでに高い評価を得ていました。巨匠黒澤明監督の「影武者」に2人が出演するのは、それから5年後のことです。
他にも森本レオ、壇ふみなど、今ではすっかりベテランの域に達した俳優たちがややぎこちなくも初々しい演技を見せています。
自立に向け旅立つとき、その胸に去来するのは
胃の中から何か苦いものがこみ上げてくる。頭の中では(やばい...トイレに行かないと...)と考えているのだが手足が動かない。その一方、アルコール漬けのぼやけた頭で前の日の夜の出来事を少しずつ思い出していた。
東京の夜はその日が最後だった。翌日は、その春入社する予定の会社の寮に向かう。上野池之端にあるいきつけのジャズ喫茶、「壷屋」で飲んだ。酒はいつものサントリー・ホワイトで、酒屋で買うと当時は確か850円くらいだったと思う。ウイスキーには暗黙のステータスがあって、「ホワイト」の上は「角瓶」、その上は「オールド(通称「だるま」)」だった。世の中に出たばかりの新・社会人たちのささやかな夢の一つは、「いつかはオールドをボトルキープ」だった。手にする物の経済価値が幸福感と比例していた時代、そしてそのことを疑う余地などなかった時代の話である。
カウンター越しにマスターといつものように話をした。マスターの声は少しかすれていて、それが話に熱を帯びてくると、時々オネエ言葉になる。本人に言わせれば全くその気(け)はないそうなのだが、慣れるまでは少したじろいでしまう。頭の回転が速く、考え方にも1本筋の通ったなかなかの人物だ。当時30歳少し前だったと思う。
この店ができたのは昭和50年の夏ころだったと思う。無謀にも当時のジャズ喫茶の老舗、「イトウ」のほぼ真向かいにオープンしたのである。しかも1階が大人のおもちゃ店、4階が風俗店という雑居ビルの3階だ。この国の人口の二分の一は、ほぼ最初から来客として望めないすばらしい立地条件であった。
当時のジャズ喫茶というのは純粋にジャズのレコードを鑑賞するところで、会話厳禁がほとんどであった。老舗と呼ばれる店はレコードも数千枚単位で保有し、音響も凝りに凝った仕様で固めていた。住宅事情の悪かった当時では考えられない、テーブルのコーヒーカップが振動するくらいの大音響で聴くことができたのである。今でもこれだけは言えるのだが、音楽はある程度の音圧でないと、聴こえてこない、見えてこない世界がある。その意味で都内のさまざまな店のさまざまな音で聴いた経験は、今でも私の大切な財産となっている。
聴きたいレコードをリクエストするときは、レコードのタイトルとA面かB面を指定し、他人のリクエストがたまっていれば、かかるまでじっと待つ。コーヒーが一杯250円くらいだったろうか。何時間居座っても追い出されることはなく、本を読んだり、新譜に聞き入ったり、それぞれが気ままに過ごせるとても豊かな空間だった。
私は「壷屋」に開店当初から通い詰めで、いつの間にかカウンターの中でマスターの仕事を手伝うまでになっていた。レコードは当初200枚もなかったはずで、客からのリクエストにもなかなか応えられないことがよくあった。それでもなぜか昭和52年の春まで、私は毎日のように「壷屋」に通ったのである。一度、ジャズ評論家のいそのてるヲ氏(現在は故人)がふらっと訪れたことがあった。マスターと少し話をしてすぐに帰られたのだが、当時の業界では重鎮であり、こんな場末のジャズ喫茶にまで足を運んでくれるなどと想像もできなかったので本当に驚いた。何かと評判のあった人だが、気さくに話している様子を見たあとつくづく思ったのは、うわさで人間を判断してはいけないということであり、音楽の愛し方は人それぞれで構わないということだった。
さて、社員寮に出発する前夜は大いに盛り上がった。映画や音楽、アート、政治、将来、異性、ありとあらゆることを話し、議論し、最後は他の客も巻き込んで店全体がダンス場になった。わけの分からないでたらめの歌詞を全員が口走りながら奇声をあげる。体が熱くなり息が切れ、足元がふらつく。しかし、止まらないのかそれとも止めたくないのか、ダンスは延々と続く。
額からは汗が流れ落ち、頬はすでにグシャグシャに濡れていた...
「青春の蹉跌」の主人公、江藤賢一郎(萩原健一) は大学の法学部に通っており、アメリカンフットボール部に所属している。彼が家庭教師をしていた大橋登美子(桃井かおり)が無事短大に合格した。お祝いのスキー旅行に出かけた二人はそこで結ばれ、恋人としての付き合いが始まる。一方、賢一郎の学費を援助している伯父(高橋昌也)は娘・康子(壇ふみ)と賢一郎を結婚させ、ゆくゆくは自分の会社を継がせるつもりでいる。賢一郎は部活を辞めて司法試験の準備を始めるが登美子との関係は続いていた。
賢一郎は康子と結婚すれば裕福で安定した将来が確約されているのはわかっていた。輝ける未来へのレール、貧困生活からの脱却は約束されている。しかし彼の表情には喜びがない。
伯父の手による予定調和の人生に対し、しらけきっている様子がありありと見て取れる。しかし誘いを蹴ってまで目指すものがあるわけでもない。受け入れるしかなかった。
彼は康子とプラトニックな交際をしつつ、登美子との肉体関係も継続させる。惰性と成り行きで生きる賢一郎のさまを、萩原健一が巧みに演じている。賢一郎が心の中でつぶやくように歌う「斎太郎節(さいたらぶし)」 が印象に残る。
"エンヤートット、エンヤートット、マツシマア~ノ"
映画のシーンとはと全く無関係、かつ唐突に発せられるこの歌が、彼の不安定で、現実とまともに対峙しようとしない、醒めきった心のうちを代弁している。
賢一郎は司法試験に合格し、康子と婚約する。そして登美子に別れを告げようとするのだが、そのとき彼女から妊娠を告げられた。すでに5ヶ月が経過しており処置できないという。彼は困惑する。登美子に愛などない。このままでは自分の将来が破綻すると考えた彼は、一つの決断をし、それを実行に移す。
司法試験の合格、そして人生の新たな船出ともいえる康子との婚約披露パーティーが華々しく催される。その瞬間が、彼の人生における一つのピークであった。賢一郎はこの後、底知れぬ闇が覆いつくす縦穴に落ちていくことになる...。
前の日の夜に「壷屋」で繰り広げられた"狂乱の宴"を思い出していると、それは急に喉元までググッと迫ってきた。(限界だ...)。
布団から這い出し、何とか立ち上がり部屋のドアを開ける。当時私が住んでいた部屋は、アパートの一番奥だった。薄暗い廊下の両脇にはそれぞれ何部屋かが並んでいる。右側の並びの中間当たりに共同便所はあった。あわてて中に入り和式の便器の前にうずくまった。呼吸が荒くなってくる。ついに強制的に胃袋をわしづかみにされ残存物を搾り出されるあの感覚が襲ってきた。(またかよ...勘弁してくれ...酒はもういい...)。このアパートで何度体験したかわからない後悔の念が、また襲ってくる。
部屋に戻り、友人の運転するトラックが到着するのを待つ。二日酔いもだいぶ治まってきた。荷物は多くない。唯一の大物だった机は、「壷屋」のマスターにもらってもらうことになっている。
トラックが着いた。荷物を積み込み、鍵を大家に返した。
その後、マスターのところに寄って机を降ろした。マスターとは二言三言、言葉を交わした。その内容は覚えてはいないが、マスターから店のカウンター越しに学んだことは身に染み付いていた。
トラックが走り出す。自立に向けた本当の意味の旅立ちである。窓から何回か振り返り手を振った。目の前を過ぎ去るものすべてに別れを告げる。さよならマスター、さよなら東京、そしてさよなら大人になる前の自分...。
ジャズ喫茶「壷屋」は今も健在である。今年で33年目になる。片や老舗のジャズ喫茶「イトウ」はバブルの頃に土地店舗とも売り払って、今はない。
昨年、「壷屋」を訪ねてマスターと話し込んだ。昔と何も変わっていない。店の内装もカウンターの様子も当時のままである。映画の主人公ほどではないにしろ、私自身の青春の蹉跌もそこには確かに残っている。
興味のある方はお訪ねいただきたい。上野ababの向かいにある仲町通りに入って30メートルほど歩いた左側の雑居ビルの3階である。今は夜のみの営業だそうだ。ジャズを堪能できるのはもちろん、この店は会話OKである。