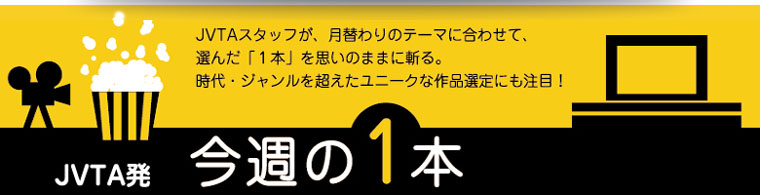vol.87 『オカルト』&『(500)日のサマー』 by 石井清猛
7月のテーマ:怖い話
「悪夢のように恐ろしい」という表現をよく耳にします。
日本語にも英語にもあり、そして恐らく他の言語にも同様の言い回しがあるとするなら、"通常の恐怖ではない"ことを示すために使われるこの「悪夢」という言葉は、それを耳にする私たちに一体どんなイメージを想起させるというのでしょうか。
そもそも人類が共通して見たことのある一番恐ろしい悪夢など決められないことを考えれば、この表現のポイントは"夢"ということになります。
現実世界のものに似ていながら全く異なる論理で起きる出来事。
自らがその一部でありながら自らのコントロールが全く及ばない出来事。
現実に知っている人物とそっくりに見えて全くの別人が登場する出来事。
アンリアルそのものなのにリアル以外のなにものでもない出来事。
途中で「これは現実ではない」と気づいても自分のその感覚を最後まで信じることができない出来事。
そんな出来事が連続して、あるいは不連続に起きる場としての夢です。
例えば恐ろしい出来事を体験して、それが夢だと分かった時あなたはホッと胸をなで下ろしますか?
もちろんそうでしょう。
でもそれは夢が終わってからの話。
もしも終わらない悪夢があるとしたら...。
誰もが悪夢の1つや2つは見たことがあるとして、そのどれが一番恐ろしいかはもはや問題ではありません。悪夢はそれが"夢である"というだけで、"普通でなく恐ろしい"のです。
「悪夢のように恐ろしい映画」という謳い文句もやはりよく耳にしますが、白石晃士監督の『オカルト』に限っては「悪夢のような映画」と言った方がしっくりきます。それほどこの作品は"夢の中で体験する恐ろしい出来事"に酷似しているのです。
しかし『オカルト』は悪夢を"コピー"した類似の作品とは決定的に異なります。
2009年に発表されたこの傑作は、悪夢のイメージをなぞっただけのどんな映画にも似ていません。
『オカルト』はホラーでもスリラーでもミステリーでもサスペンスでもなく、むしろそれらすべての要素を含みながら、最終的に映像自体の"オカルティズム"に触れてしまうような、真に「悪夢そのものの映画」です。
2005年に東海地方の観光地で起きたある通り魔事件の真相を追う映像作家の白石。観光客2名を殺害し1名に重傷を負わせた犯人は崖から身を投げ行方不明となっている。白石は惨劇の一部始終が撮影されていた観光客のビデオを手がかりに、関係者インタビューなどの調査を進めていくが、彼の取材は唯一の生存者である江野と出会ったことで思わぬ展開を見せ始めるのだった...。
"フェイクドキュメンタリー(mockumentary)"という言葉を知っている皆さんであれば既にお分かりと思いますが、映像作品においてドキュメンタリーとフィクションを隔てるいかなる境界線も存在しません。
映像作家の白石が追う事件がこの世に実在しようがしまいが、『オカルト』の映像は"現実世界のものに似ていながら全く異なる論理で起きる出来事"を"アンリアルそのものなのにリアル以外のなにものでもない出来事"として描き出すばかりです。
そこで私たちが出会うのは"悪夢のような映像"と"映像のような悪夢"の一体どちらなのでしょう。
あるいは白石晃士は、本当は悪夢が映画の"コピー"であることを示そうとしていたのかもしれません。
そしてもう1本。私が近年見た中でダントツに恐ろしかった映画。
腹わたが煮えくり返るほどムカつくのに愛しくてたまらない映画。
この映画を高1の時に見たのでなくて本当によかったと思ったのはきっと私だけではないでしょう。
つまり『(500)日のサマー』です。
この世界に実在する悪夢の1つに、お互いに運命の人と信じ合っていると思っていた相手に"私はそうは思ってなかった"と告げられる瞬間というのがありますが、これほど確かな恐怖すら、年を重ねるごとにやがて薄まっていくものなのでしょうか。
ヘッドホンから漏れるザ・スミスも、イケアのシステムキッチンも、カラオケの「明日なき暴走」も、コピー室のキスも、全部なかった方がよかった。なんて頑なに思えたはずの日々は過ぎ去ったままなのでしょうか。
その答えが何であっても、私は決してベッドに横たわって天井を見上げるズーイー・デシャネルの目の色を忘れたりしないでしょう。
─────────────────────────────────
『オカルト』
監督・脚本・撮影・編集:白石晃士
音楽:Hair Stylistics
出演:宇野祥平、野村たかし、栗林忍、東美伽、近藤公園、ホリケン。、
吉行由実、白石晃士、高槻彰、渡辺ペコ、黒沢清、鈴木卓爾ほか
製作年:2008年
製作国:日本
『(500)日のサマー』
監督:マーク・ウェブ
製作:マーク・ウォーターズ、ジェエシカ・タッキンスキーほか
脚本:スコット・ノイスタッター、マイケル・H・ウェバー
撮影:エリック・スティールバーグ
音楽:マイケル・ダナ、ロブ・シモンセン
出演:ジョセフ・ゴードン=レヴィット、ズーイー・デシャネル、
ジェフリー・エアンド、クロエ・グレース・モレッツほか
製作年:2009年
製作国:アメリカ
─────────────────────────────────